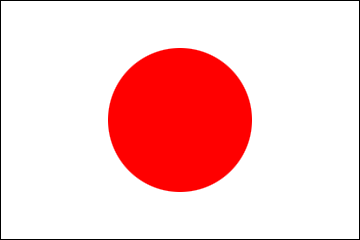戸籍・国籍関係の届出
令和7年5月26日
※当館では、領事窓口の混雑を分散し、皆様の待ち時間を軽減させることを目的として、領事窓口は事前予約制でご来館頂いておりますので、窓口のご利用に際しては、電話(06-1-398-3100(代))で予約をお取りいただくようお願い致します。領事窓口をご利用される皆様の利便性のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。なお、緊急の場合など、特別なご事情がある場合には、ご相談ください。
1.日本人と外国人との間の創設的な婚姻届、日本人と外国人との間の創設的な離婚届等、在外公館で届け出ができない場合もありますので、ご注意ください。
2.在外公館での戸籍関係の届け出は、新たな身分事項の発生、または、身分事項の変更があった日から起算して3か月以内に行う必要があります(戸籍法第104条第1項)。
特に、日本人と外国人との間の子の出生届は、届出期間を経過した場合、子が日本国籍を留保することができない可能性があるので、届け出はなるべく早めに行うようご注意ください。
3.当館で受理した届出書は、日本の外務省経由で本籍地の市区町村役場に送付され、市区町村役場にて戸籍の届出事項が登録されます。従って、当館に届け出てから戸籍に反映されるまで、1か月以上かかりますのでご注意ください。
4.窓口での手続きに時間を要しますので、窓口時間終了の30分前までに余裕を持ってご来館ください。
| 戸籍 | |
|---|---|
| 婚姻届 | 日本人とハンガリー人、又は日本人同士で結婚する際の届出 |
| 離婚届 | 日本人とハンガリー人、又は日本人同士で離婚する際の届出 |
| 出生届 | ハンガリーでお子様が生まれた際の届出 |
| 死亡届 | 日本人(同居家族、同居者等)が死亡した場合の届出 |
| 不受理申出制度 | 本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度 |
| 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて | |
| ハンガリー方式における婚姻手続きについて | |
| 国籍 | |
|---|---|
| 国籍選択届 | 『日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します』 との国籍選択宣言に必要な届出 |
| 外国国籍喪失届 | 重国籍者が外国国籍を喪失した場合の届出 (ハンガリー国籍を喪失した場合等) |
| 国籍(日本国籍)喪失届 | 自己の志望により外国の国籍を取得した場合、 又は重国籍者が外国の法令により外国の国籍を選択した場合の届出 |
| 国籍(日本国籍)離脱届 | 重国籍者が日本国籍を離脱したい場合の届出 |