在ハンガリー日本大使館 館員日誌
平成22年(2010年) 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
平成21年(2009年) 12月 | 11月 | 10月 | 9月
マンガリッツァ農場訪問
2010年10月27日
 |
| マンガリッツァ豚(子豚にはウリ坊のような縞模様があります) |
 |
| 全国マンガリッツァ生産組合長のトート氏とともに |
10月27日、ブダペストから東へ約160キロのエメード村近郊にある「マンガリッツァ」の農場を伊藤大使他と訪問しました。
マンガリッツァはハンガリー固有の高級食用豚です。その希少性から国が「国家遺産」として認定しており、また世界で唯一全身が縮毛で覆われている豚であることから、「食べられる国宝」、「羊毛の豚」とも呼ばれています。19世紀にハンガリー在来種に地中海地方原産種等を掛け合わせて作られ、スペインのイベリコ豚と同じルーツを持っています。
1950年代までは輸出のために盛んに生産されていましたが、出荷出来るまでの生育期間が一般の食肉用豚の2倍以上と長いこと等から生産農家が徐々に減少し、1990年初めには世界で合計198頭が残るのみの絶滅の危機に瀕しました。今回農場を案内してくれたトート・ペーテル氏は、留学先のスペインで畜産を学び、スペインの食品会社の依頼を受け、ハンガリー政府の協力も得て、1991年からマンガリッツァの保護・増産に努め、2000年からは再び一般販売出来るようになるまでマンガリッツァの生産を回復させました。
トート氏によれば、マンガリッツァの肉質はイベリコ豚よりも柔らかく、いわゆる「サシ」が入った霜降り肉で、油の舌触りや香りが非常によいと評されています。この理由については、ハンガリー産のヒマワリの種などを摂取していることや、冬にも暖房を使わないなど自然環境に近い状態で飼育されていることも非常に重要であるとのご説明を受けました。2009年3月のFOODEX JAPAN(アジアで最大の食品・飲料展示会)で紹介されて以来、マンガリッツァは日本においても人気を伸ばしているとのことです。(経済班:N.A.)
ヴェスプレームでの「日本の日」
2010年10月12日
 |
| 盆栽展の会場にて主催3団体の幹部と共に |
 |
| 当館館員が「日本の魅力と日本への留学」について講演 |
10月9日、ブダペストから西へ約120kmのヴェスプレーム市で開催された日本文化紹介行事「日本の日」の開会式に出席しました。
ハンガリーは、西暦1000年に初代国王の聖イシュトヴァーンがカトリックの洗礼を受けてカトリック王国となりましたが、ヴェスプレームは、歴史上初の司教区が設置され、現在もハンガリーに4つある大司教区のひとつが置かれているカトリック教会の拠点であり、また、イシュトヴァーンがギゼラ王妃のために同地に建てた宮殿に歴代の王妃が住んでいたことから「王妃の町」としても知られています。
先月、日本企業の奨学金授与のために同市のパンノニア大学を訪れましたが(館員日誌)、ヴェスプレーム県は、これまで12年以上岐阜県と友好交流を続けてきており、また、昨年国交樹立140周年の機会に、地元の親日家の尽力により、ハ・日友好協会の支部が設立されました。(地方自治体交流・ハ日友好協会の分布図)今回の「日本の日」は、その新しい友好協会が、ヴェスプレーム県とパンノニア大学と共同で主催したもので、2日間にわたり、伝統文化からアニメまで、幅広く日本の文化が紹介されました。
ところで、今月4日にヴェスプレーム県のアルミナ工場の廃棄物貯蔵池が決壊して、有毒な赤泥が大量に流出し、大規模な環境破壊を伴う深刻な事態を招いていますが、この工場があるアイカ村は、ヴェスプレームから西約27キロの地点に位置しています。私は、開会式の挨拶の冒頭、日本政府を代表して、亡くなられた方々のご遺族に哀悼の意を表すると共に、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げました。入院中の方々の健康が一日も早く回復し、環境汚染の除去と被災地の復旧の作業が進捗することを祈りたいと思います。(館長T.I.)
『1000のハンガリーの俳句』出版発表会
2010年10月5日
 |
| 壇上,左から,ヴィハルさん,この本の出版社のソンディ社長,この日,俳句を朗読した俳優,パップ氏。 |
10月5日、ブダペスト市内の書店で行われた『1000のハンガリーの俳句』(Ezer Magyar Haiku)出版発表会に大使夫妻と共に参加しました。この本は,ハンガリー・日本友好協会の会長で,ブダペストの大学の日本語学科で俳句や翻訳を教えているヴィハル・ユディットさん(館員日誌)が選者となり,季節,愛,生と死といった25のテーマ別に282人のハンガリー人の俳句が紹介されています。
ヴィハルさんによると,ハンガリーで俳句が広まりだしたのは80年代以降のことですが,既に20世紀初めにはハンガリーに俳句が紹介されており,当時は,英語やドイツ語からの翻訳という形だったそうです。そのころは5・7・5(音節)のルールは遵守されていなかったようですが,60年代以降からは守られるようになっているそうです。
最後に,ヴィハルさんの作品を紹介します。ハンガリー語でも,みごとに5・7・5の音節になっています。季語は「梨」です。(日本語訳は,俳人の吉村侑久代さん)。
Ma/dár/csi/cser/gés, (5) 鳥鳴きや
vi/rág/zik/a/kör/te/fa, (7) 梨が散るとき
gu/lyás/ill/at/száll (5) グラシ薫る
(※「グラシ」は,ハンガリー名物のグヤーシュスープのこと)
(広報・文化班:K.Y)
東洋シートへの訪問
2010年10月1日
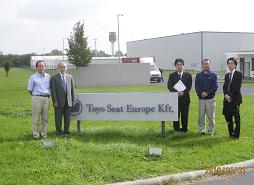 |
| 日本人幹部の方と工場入口にて |
10月1日(金)、東洋シート・ヨーロッパ(正式社名:Toyo Seat Europe Kft.、従業員数:約200名)を訪問しました。
親会社の東洋シート(本社:広島県安芸郡)は、自動車用シート及びその機構部品等を製造販売する会社です。東洋シート・ヨーロッパは、その欧州最初の製造拠点として、2002年、サーズハロムバッタ市(ブダペストの南約30km)に設立され、自動車用シートフレームやシートスライド(座席の位置を前後に調整するための器具)等の機構部品を製造しています。製造工程としては、上記部品のプレス、溶接、組立て及び塗装が行われており、その随所に従業員による改善活動を通じて考案された作業効率化の工夫が生かされているとのお話を伺いました。同じ車種であっても、モデルチェンジ毎にシートのデザインが変わるとのことで、大型の機械と何種類ものプレス用金型が並ぶ製造現場では、ハンガリー人の従業員が真剣に作業に取り組んでいました。(経済班:S.H.)
